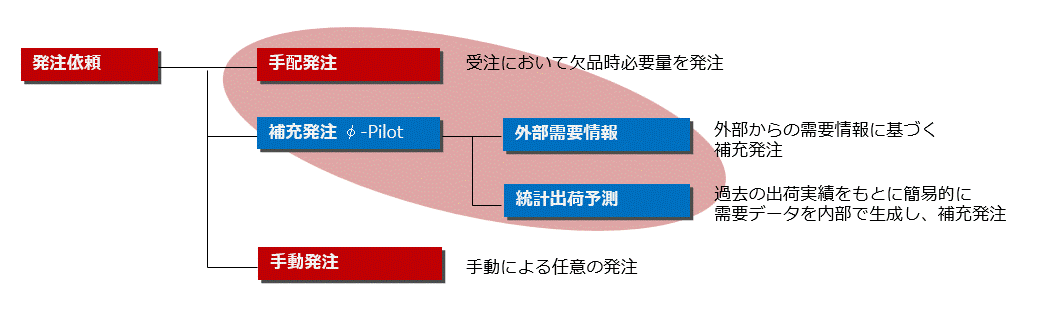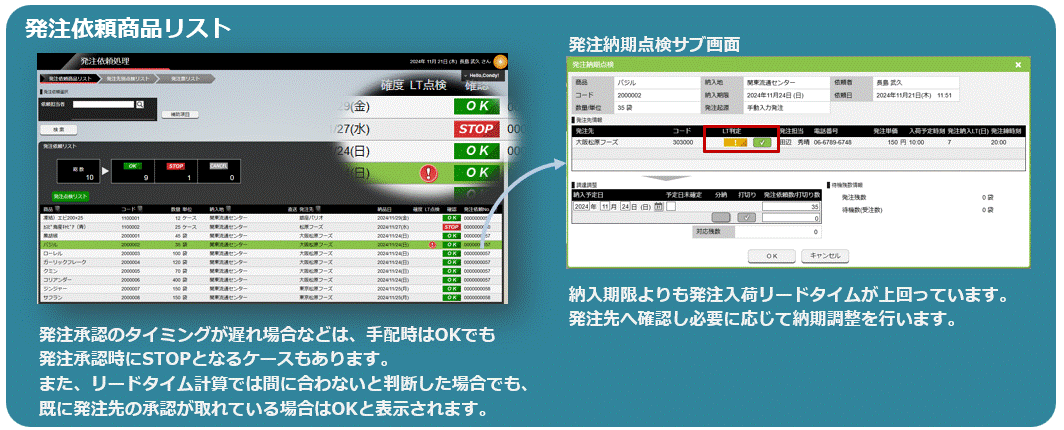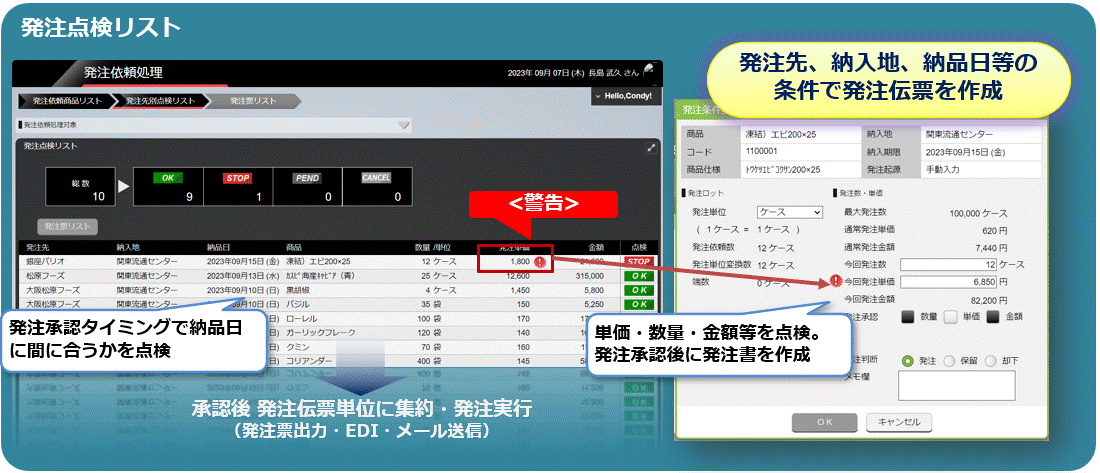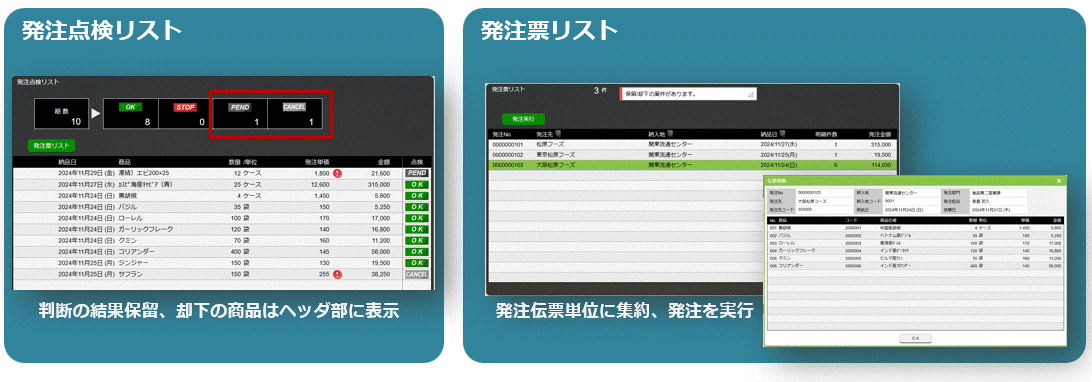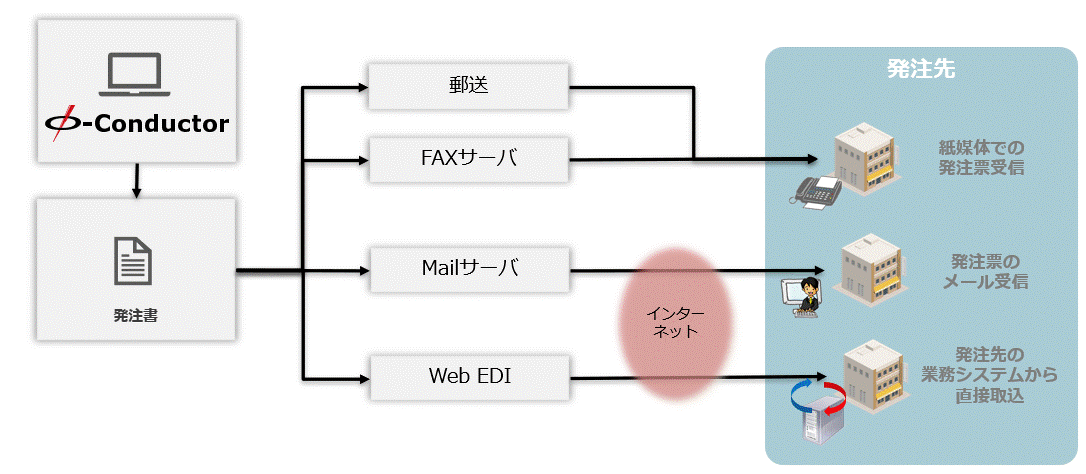発注依頼処理
手配は補充計算結果から作成された発注依頼情報の数量・単価・金額・納期等の点検を行い、発注先への発注を行います。
発注依頼の起源
発注依頼情報は、手配(受注を起源にしたもの)、自動補充発注計算、発注依頼入力画面からの直接入力の3つの起源から作られます。
手配発注 -
受注100個に対して、在庫が80個しかない場合、
顧客が注文をキャンセルしなければ、20個の発注をかけることになります。
受注に対する必要数の発注ですから、無駄な発注をしているわけではありません。
このような発注を「手配発注」と呼んでいます。
補充発注 -
では、80個の在庫は何故あったのでしょうか?
これは、過去に将来の注文に備えて発注を行った結果です。
このような発注を「補充発注」と呼んでいます。
前提となるのは、将来「売れるであろう」と思われる販売見込み(需要)が考慮されていることです。
補充発注については、φ-Pilotで運用します。
手動発注 -
在庫とは無関係に、人の判断でかけられる発注です。
「今、安いので買っておこう」とか、「サプライヤからの依頼で発注」ということもあるでしょう。
φ-Conductor、φ-Pilotでは、手動発注を除いて、手配発注、補充発注はシステムが作成し、それを在庫状態に応じてコントロールします。
発注依頼処理
発注依頼データは発注依頼処理によってルールに応じた処理を行います。発注先や商品を取りまとめたり、発注数や金額をチェックし予め設定した値を上回ると警告を画面から表示します。
発注担当者の担当すべき発注対象をワークフローに従って対象案件を一覧表示します。手配発注、直送依頼、手動発注依頼、補充発注依頼からの起源があります。希望納期とリードタイムの点検、入荷予定の確度(予定・確定)の確認などを行います。
発注数量、単価の点検行い、発注承認の点検を行います。標準単価との乖離がある場合には、発注承認者に通知します。
発注先、納期別に伝票形式に集約します。確認をし実行することで発注が確定します。発注書は、EDI、メール等の通知手段に合わせて必要なデータを生成します。
発注依頼処理:発注実行と保留・却下
発注については、直前で「ストップ」や「却下」をかけることありえます。発注処理中においても「ストップ」がかかった案件については、「保留」という形でとめることができます。
「却下」された発注依頼は依頼担当者に「却下」内容が通知されます。必要に応じて「却下」理由も記載されます。手配からの発注であれば、対象の伝票は手配不可として再手配に回ります。
「発注実行」が押下された段階で、システムは発注票を発行し、発注がなされたものと見なします。実際に発注先に発注票が届いたかどうかまでは、φ-Conductorでは、捉えておりません。
発注票出力
φ-Conductorでは、発注実行がなされ、発注票を作成時点で発注がかかったものします。
企業間取引においても物理的書面の郵送ではなく、インターネットを介した情報交換が主流となっていますが、発注先によってはFAXも利用されています。
現在、φ-Conductorは、発注票出力について、 CSV形式※によるドキュメント出力を標準機能としています。CSV形式からExcelフォーマット、PDFフォーマットに切り替えるなどさまざまなバリエーションが可能です。
データの送受信は、顧客・倉庫であっても同様の連携が可能です。
発注ロットまとめ
発注先との取引条件によっては、最小発注ロットや最小発注金額が決まっている場合や、物流コストを削減する為に、複数商品をまとめて発注するケースがあります。
このような“まとめ発注”といった業務についても支援します。